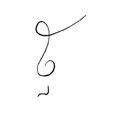…また笑った、楽しむように穏やかに。恐らく彼女と。
小さな蝶は、その前の、石の壁の上の生命のない翅々を見た。
「あなた、いつも訳あってするからには、」 と囁いた、「この全ての理由を言って?」
しかし王は多分彼女の言葉を聞いていなかっただろう、何故なら少しも笑っていなかった。
ただ時間が経ってから、黙って窓際に近付いた。前に屈んだ。その眼下には色鮮やかな彼の庭園が見て取れた。蝶の翅に溢れて…
話し始めた。小さな囚われの身よりも風のに向かって饒舌に。「…彼らのうちの多くは」言って、彼らと分かち合ったあらゆるものを思い起こしながら… 今となっては遠い昔…
「…彼らのうちの多くは、決してこの大広間には辿り着かないだろう。
少なくともまだ飛べるうちに。」
「彼らのうちのどれかは、私には全くもって興味がない…
彼らの翅の形や色、決して私の目を楽しませるものではなかった…
私の庭園の回廊に消えて失せるだろう。そして一瞬たりとも生きなかったかのように。」
「他もまた、私を少しも困らせなかった。
私が与えた神酒に漬かり そしてそれに生涯を酔わせるに足りた。」
「最後に、彼らのうちに、また別の蝶たちがいた…」
「どれか恐らく僅かな、恐らく結構な数、もう覚えていないかつてこの大広間まで辿り着いたのが。理不尽にも私に立ち向かえると思ったのが。
しかし彼らもいつかは選ばなければならなかった… 一瞬だけの死。
或いは終わらない命の延長。」
「何を選んだか知ってるだろう。
君もいつか選ぶだろうあらゆるもの… 他に選択の余地はなかっただろう。」
「ほら 彼らを見てご覧!
私の庭園を飛んでいる。私の近くを飛び そし
彼らの翅の形や色、決して私の目を楽しませるものではなかった…
私の庭園の回廊に消えて失せるだろう。そして一瞬たりとも生きなかったかのように。」
「他もまた、私を少しも困らせなかった。
私が与えた神酒に漬かり そしてそれに生涯を酔わせるに足りた。」
「最後に、彼らのうちに、また別の蝶たちがいた…」
「どれか恐らく僅かな、恐らく結構な数、もう覚えていないかつてこの大広間まで辿り着いたのが。理不尽にも私に立ち向かえると思ったのが。
しかし彼らもいつかは選ばなければならなかった… 一瞬だけの死。
或いは終わらない命の延長。」
「何を選んだか知ってるだろう。
君もいつか選ぶだろうあらゆるもの… 他に選択の余地はなかっただろう。」
「ほら 彼らを見てご覧!
私の庭園を飛んでいる。私の近くを飛び そし